

住宅の2025年問題 【空き家】
住宅の2025年問題

不動産建築業界において、2025年の建築基準法改正が大きな話題となっています。この改正には住宅の断熱効果や省エネ基準の厳格化が含まれており、不動産市場に大きな影響を及ぼすことが予想されます。ここでは、2025年の建築基準法改正について詳しく掘り下げ、その影響と対策について考察します。
現在、日本では省エネ住宅の義務化が行われておらず、建売住宅や自宅建築において省エネ性能を考慮しない場合があります。このため、購入前にしっかりと情報を確認する必要があります。
また、一部の営業マンや広告では「断熱性が最高」といった表現がされていますが、実際には世界的な省エネ基準には達していない場合もあります。2025年4月までは省エネ住宅でなくても建築が可能ですが、将来的なエネルギーコストの増加や快適性の低下を考慮すると、性能の高い住宅を選ぶことが重要です。特に長期優良住宅と呼ばれる基準に適合した住宅はおすすめであり、省エネ性能やメリットについて詳しく調査することが求められます。
改正の経緯
この改正は、2022年6月に実施され、住宅省エネ基準に関する大きな変更が行われました。以前、この基準は2010年に導入され、その後延期されたり取り下げられたりしてきましたが、2022年にようやく改正が決定しました。改正の実施は2022年度から始まり、これにより建築業界には大きな変化がもたらされることになります。2025年における建築基準法改正は、政府が住宅の建築基準法を改正する一環として行われます。この改正において、特に注目されているのが省エネ基準の厳格化です。現行の法律では、木造住宅において省エネ基準の適合義務は説明程度でしたが、2025年以降は適合義務が確実に通さなければならないレベルに引き上げられます。これに伴い、断熱材の強化や基礎の断熱などが必要とされ、住宅の基準が厳格化されることが予想されます。
主要な変更点
新たな住宅省エネ基準にはいくつかの主要な変更点があります。以下にその概要をまとめてみましょう。
- 2025年から、省エネ性能が低い住宅の建築が制限される。
- 等級4以上の省エネ性能を持つ住宅が要求される。
- 2022年4月1日から、新しい基準が適用される。
これらの変更により、住宅の建築においては省エネ性能がより重要視されることとなり、建築業界における新たな課題が生まれることでしょう。
既存の住宅との関係性
新たな基準が導入されることで、既存の住宅にどのような影響があるのでしょうか。実は、既存の住宅の多くが既に省エネ性能を持っていることが示されています。2019年の調査によれば、既存の住宅のうち81%が新たな基準に適合しているとされています。つまり、2025年の制限が実施されなくても、既存の住宅の多くは基準を満たしているということです。
4号特例の撤廃
建築基準法改正のもう一つの注目ポイントは、4号住宅の撤廃です。これは、2025年以降に建築される木造住宅で、2階建てかつ200平米以下の建物に該当します。従来、4号住宅特例は検査が少なく、比較的緩和された基準で建設が行われてきました。しかし、これが撤廃されることで、木造住宅においても構造計算が必要となります。これは安全性の確保に寄与しますが、新築やリフォームの際に追加の負担となる可能性があります。
リフォームとリノベーションの影響
建築基準法改正は、新築だけでなく、リフォームとリノベーションにも影響を与えます。以前は昭和56年6月以降の建物に対して新耐震としてのローンが通りやすかったが、改正により適合証明の取得が難しくなる可能性があります。これが、不動産の市場におけるリフォームやリノベーションに新たなハードルを設けることにつながります。
住宅の選択と将来の展望
これからの不動産市場において、消費者は慎重に選択を検討する必要があります。予算、ローンの返済期間、省エネ要件などを考慮し、適切な住宅を選ぶことが重要です。また、将来的には建築基準法の改正が進行することが予想され、安全性や省エネ性に配慮した住宅選びが求められるでしょう。
【2025年問題】新築住宅省エネ基準義務化でどう変わる?

2025年に住宅の省エネ基準が改正され、不動産業界に大きな変化がもたらされるのです。 これにより、建築基準法が改正され、住宅の断熱効果などの権利が免除されます。
省エネ基準の改正
2025年には新たな建築基準が導入される予定です。これにより、建物の構造的な安全性や性能基準がより厳しく求められるようになります。政府が住宅の建築基準法を改正し、省エネ基準を強化します。これにより、木造住宅においても断熱材の性能向上や基礎の断熱などが必要とされるようになります。長期運用住宅の基準に基づき、住宅の断熱性能が重要なポイントとなります。 環境問題の意識の高まりに伴い、建物の省エネルギー性能が重視されます。2025年以降は、よりエネルギー効率の高い建物や低消費エネルギー設備が求められるでしょう。
地震対策の強化
地震のリスクに対する意識が高まっています。2025年以降は、より耐震性の高い建物が求められ、地震時の安全性が重視されます。耐震基準の向上や地盤改良などが注目されます。
構造計算の必要性
2025年からは木造住宅の2階建てや200平米以下の建物にも構造計算が必要とされます。これまでは特定の条件下では構造計算が不要であった4号住宅が廃止されるため、建築の安全性の確保のために構造計算が必須となります。
リフォームやリノベーションの影響
新しい基準に基づくリフォームやリノベーションの影響が出ます。適合証明やローン取得が正義にもなり、手続きが厳しくなります。これにより、住宅の販売においては困難さが増し、必要が新築や解体しての建て替えに移行する可能性があります。
既存建物の対応
2025年問題として知られる課題が存在します。これは既存の建物が新しい基準に適合していない場合に不適合とされる可能性があることを意味します。これにより、改修やアップグレードが必要となる建物が出てくる可能性があります。
建築基準法改正の歴史
建築基準法は過去に何度も改正が行われており、新耐震や構造計算の重要性が強調されてきました。耐震基準は長らく改正されず、今回の改正で大幅に強化されます。
不動産業界はこうした変化に対応するため、建築技術の向上や省エネ対策の充実、新しい基準に適合した住宅の供給などに取り組む必要があります。
住宅の2025年問題【断熱性】
- 2025年には断熱等性能等級4を満たした省エネ住宅が最低ラインとなり、それよりも断熱性能が低い住宅は建てられなくなります。
- 国家政策目標により、2050年までにカーボンニュートラルを実現する必要があり、省エネ基準の義務化が進められています。
- 断熱等性能等級6以上の家づくりが必要であり、湿気対策や機密性の確保が重要です。
- 気候風土に合った断熱材の選択が必要であり、フェノールフォームなどの高性能な断熱材が推奨されます。
- 断熱性と機密性の確保が重要であり、C値が低い設計を目指す必要があります。
- パッシブ設計により日射をコントロールし、高断熱高気密ながら快適な居住環境を実現します。
- 最低レベルの合理基準適合では各種補助金の利益が消去できます。
2025年から省エネ基準が義務化され、断熱等性能等級4以上を満たす住宅が最低基準となります。これまでの日本の住宅の断熱基準は、23年前の次世代省エネ基準とは少し変わっていますそのことなく、日本の住宅の断熱性能は先進国の中では最低レベルとされています。省エネ基準の義務化は、2050年までにカーボンニュートラルを実現し、2030年までに温室効果ガスの46%の排出削減を目指す国家政策目標に基づいて行われています。日本も脱炭素の流れに追従し、省エネ基準の義務化が必要とされています。
日本の特徴としては、雨や雪の多い日と高湿度が挙げられます。そのため、湿気対策した断熱性と性能等級6の家づくりが重要となります。北陸の気候風土に合った断熱材の選択が挙げられます。フェノールフォームなど、湿気に強い断熱性能の高い材料が推奨されます。また、機密性の確保も重要です。C値と呼ばれる機密性の基準を下げることで、断熱性能を高めることができます。目指すべきはC値0.5以下です。さらに、日射を制御するパッシブ設計も重要です。高断熱高気密ながら、夏は涼しく冬は暖かい居住環境を実現するために、設計によって日射を取り入れ方や調整を行います。
長期優良住宅のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)レベルも2022年に導入されました。ZEHとは、年間のエネルギー消費量と再生可能エネルギーの発電量がほぼ同等になる住宅のことを言うこれにより、住宅の持続可能性や省エネルギー化が重視されるようになりました。過去20年間にわたり、建築の断熱性能基準は変更し続けてきました。 初めての省エネルギー基準は1980年に導入され、その後の新省エネルギー基準や次世代省エネルギー基準の見直しにより基準値が変更されてしまいましたしかし、過去には断熱性能があまり重視されず、低い性能の住宅が建てられることがありました。
1997年の京都議定書をきっかけに、省エネルギーは光熱費の削減だけでなく、CO2排出削減や環境問題への対応という観点からも重要視されるようになりました。に進められるようになりました。しかし、基準の変更は急ぐだけでなく、強制力がなくても低い断熱性能の住宅が建てられることもありました。業界全体のレベルアップの遅れや技術的な課題などが影響していました。2013年には高断熱住宅の義務化が計画されましたが、業界の準備不足技術面の課題から延期されました。このため、2020年以降に義務化予定されるであった高断熱基準に達していない住宅も建てられることになりました。
現在は、長期優良住宅の認定基準によって高い断熱性能が求められています。これにより、地域型住宅グリーン化事業や住宅ローン権利などの瞬間措置が提供されるようになりました。からは断熱基準の追加が行われ、より高い性能の住宅が建てられるようになりました。2030年までには、全ての新築住宅が高い断熱性能を備えることが目指されています。これは、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの堅実として位置づけられています。高断熱化が進むことが期待されています。
※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。
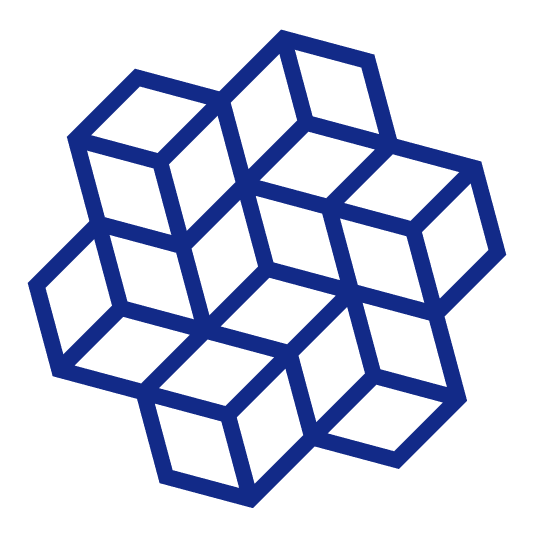





.jpg)



.jpg)