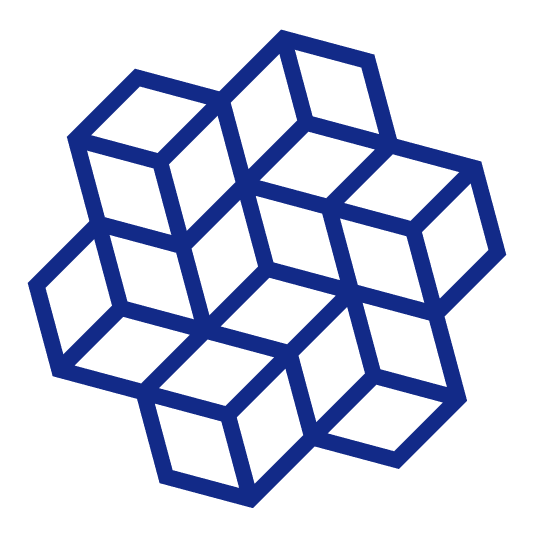地鎮祭に必要とされる具体的な費用とは、一体いくら位なのでしょうか。土地や地方、規模によもよりますがかなり幅があります。必要になってくる費用と、基本的な地鎮祭の流れをご紹介します。
地鎮祭の流れ
地鎮祭にかかる費用を知るためにも、まずは地鎮祭そのものの流れをご紹介しましょう。
手水(ちょうず)
神事のために設けられた会場(一般的にはテント)に入るため、手水桶から汲んだ水で手を清めます。タオル代わりの手拭紙を渡されます。
開会の辞
挨拶は建て主、お客様が行うのが本来のスタイルですが、最近では多くの場合、神主さんが行っています。また、地鎮祭の規模が大きくなると、司会者がいるケースがありますので、その場合は司会者が行うこともあります。
修祓(しゅばつ)
参列者やお供え物を清める儀式です。神主が大麻(おおぬさ)を手に持ち、お供え物や来場者に向けて左右に払うしぐさをします。
降神(こうしん)
会場に設けた祭壇に神様をお迎えする儀式です。神主が唸るような発声をし、神様をお呼びします。
献饌(けんせん)
お酒とお水の入った容器のふたを開け、神様にお供え物をささげる儀式です。
祝詞奏上(のりとそうじょう)=土地に建物を建てることを神様に告げ、工事の安全を願います。施主や設計者、施工業者の名前を含んだ祝詞を読み上げます。
四方祓(しほうはらい)
敷地の四隅を清めます。神主は一度テントから退出し、土地の縁をお祓いします。
地鎮(じちん)
この儀式は、設計者及び施主と施工者が初めて土地に手をつけるという意味があります。神前に作った草やススキを立てた盛砂に、設計者や施主、施工業者が「忌鎌(いみかま)」、「忌鍬(いみくわ)」、「忌鋤(いみすき)」を入れます。白木で作成されたものを使うのがよいとされていますが、実用の品でもよいとされてきています。土地から雑草を刈り取り、土をほぐし、土地を敷き均す作業を表現するものです。施主は、盛り砂の砂にクワを入れるようなしぐさを行い、「えいっ、えいっ、えいっ」と3回力強く声を出します。
玉串奉奠(たまぐしほうてん)
榊(さかき)の枝に紙垂を結んだもの「玉串」を工事の無事安全を祈って、神様(祭壇)にささげます。施主の家族と工事関係者、当日の列席者の全員が行います。
撤饌(てっせん)
お供え物を下げるために、お酒やお水の容器に蓋をします。
昇神(しょうしん)
神様を御座所にお戻りいただく儀式です。降神(こうしん)と同様に、神主が唸るような発声をします。
神酒拝戴(おみきはいたい)
神様にお供えしたお酒を頂戴します。
直会(なおらい)
地鎮祭の後に、お供え物のお下がりを食事として頂きます。会場を別に設け宴の形式で行ったり、関係者や近隣の方へお弁当を準備しお渡しすることもあります。
※お酒の席となるのが通常ですが、飲酒運転の予防のために、神酒拝戴(おみきはいたい)も口を付ける真似だけで実際には飲まず、日本酒の小瓶をお弁当に付けて配布することが増えています。
地鎮祭の費用
地鎮祭の費用は「神主への玉串料」「テントなどのレンタル料」「お弁当やお供えの代金」の3つに大別することができます。地域や地方、地鎮祭の規模によって金額は変わってくるものの、全国的な平均金額は以下のようになります。
「神主への玉串料」
お車代を含めて玉串料 3~5万円
「テントなどのレンタル料」
テントや祭壇など神事に使用する資材の設営料・レンタル料 約10万円
「お弁当やお供えの代金」
供えの代金 約2万円
お弁当代は1食あたり約3,000円~5,000円位が相場です。参列者の人数にもよりますが、20万円~30万円位用意しておいたほうが良いでしょう。
「祝儀」
地域、地方または地鎮祭の形式によっては、建築関係者へご祝儀を渡すことが一般的なこともありますので、事前に確認が必要です。
施主がこれら全て準備することもありますが、最近では建築業者が全てを滞りなく手配してくれるケースがほとんどです。その場合自身で用意する場合より、かなり割高になるのは理解しておいたほうが良いでしょう。地元のイベント業者に依頼することで一式の手配が完了することもあります。
地鎮祭は工事が始まる前に
氏神様に土地の利用をお許しいただき、工事の無事とその後の生活の安泰をお願いする儀式ですので、地鎮祭は必ず工事の前に行います。地盤改良が必要なのであれば、もちろんその前に行うものです。神式ならば六曜を気にすることは不要と言われますが、一般的には「大安」「友引」「先勝」が好まれる傾向にあります。このため、天候の安定した季節の大安・友引・先勝では、結婚式と同様にレンタル業者が忙しくなりますので、地鎮祭の日取りを決めたら早めにレンタル業者にお願いをしましょう。もちろん神主さんも忙しくなり、スケジュール調整できない場合もあります。
早め、早めに決めておきましょう。
地鎮祭にふさわしい服装とは?
特に決まっていません。普段着でも大丈夫ですが、儀式の後で写真も取られると思いますので、ラフ過ぎない程度の服装がお勧めという意見もあります。スーツの方が無難と言う方もいますが、しかし実は半数以上の方が普段着なのが実情です。ウェブ上の建築ブログやそのほかを見ても、普段着の方が多いようです。
相場がわからない場合は?
地鎮祭に必要な費用の相場がわからない時は、地元のイベント業者や資材レンタル業者をネットで検索してみてください。「地鎮祭 レンタル」などのキーワードで検索すれば、詳しく内容が書かれたサイトが出てくるはずです。レンタル資材の内容の記載や、その土地での平均的な費用や形式などの追加情報を手に入れることができます。地域での慣習(建築関係者へご祝儀やご近所への気遣いなど)についても問い合わせてみましょう。建築業者が地域密着の業者であれば、この辺りのアドバイスもしてくれるでしょう。
地鎮祭を行わないときは?
地域の風習や時代の変化と共に、特に都心部では地鎮祭を行わない傾向になりつつあります。距離的理由、時間的理由などから正式な地鎮祭ができないというケースもあります。こういった場合は、簡易的な儀式で済ませることも可能です。
なかには全く何もしなという方もいらっしゃいますが、少し心もとないものです。簡易的な儀式の場合は、土地の四隅の土を取り、その土を持って家族全員で神社へ出向き、お祓いをして頂いた上で、地鎮札を頂いて土地に戻ります。お祓いをして頂いた土を土地の四隅へ戻すと同時に塩と酒で清めます。頂戴した地鎮札は必ず建築業者に渡し、基礎工事の前に土地の中心へ埋めてもらいます。このような簡易的な地鎮祭の場合、神主さんへの玉串料は1万円~2万円程度が相場とされています。
地鎮祭と対となる「上棟式」
地鎮祭は行うけれど、上棟式は行わないケースも最近では増えています。元々はこの二つの儀式は対をなしていました。基礎工事から始まった工事も、梁や柱など骨組みが完成したのちに棟木を取り付ける際、いわゆる棟が上がった時に行うものです。神事ではありませんが、四隅の柱に塩や酒や米などを撒き、この後も工事が無事に進むようにと祈願する風習です。地方によっては、ご近所のみなさんとのご縁が結ばれるよう5円玉に専用の紐を水引風に結わえたり、お餅を包んだりして、配ったり撒いたりします。
※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。