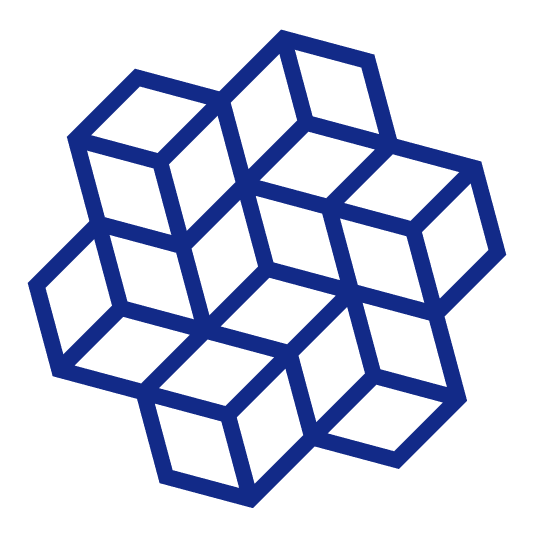柔軟な対応とアイディアが「建築家」「設計事務所」の特徴
【PR】

建主の希望に建築家のアイディアをプラスして、極めて困難な条件でもクリアできる魅力があると言えます。家づくり、注文住宅といえば、すぐに「ハウスメーカーか工務店」を思い浮かべる方が多いでしょう。しかしこの二者択一、という時代は昔の話なのです。家づくり、注文住宅の依頼先として、建築家(設計事務所)を選択肢に加えることが、今では常識になりつつあります。建築家や設計事務所は『敷居が高そう』というイメージがありますが、実はそうでもないのです。住まいにこだわりをもつ人がふえてきたことなどから、よりよいパートナーとして建築家や設計事務所に大きな注目が集まっています。
【目次】
【PR】 タウンライフ
悪条件や予算が限られた人こそ「建築家」がお勧め!!

現実的に、「自分たちだけのオリジナリティのある家をつくりたい」という建主にとって、建築家は最適の依頼先と言えるでしょう。個性的なデザインはもとより、一軒一軒のライフスタイルを考えたプランを提案してもらえることが大きな魅力です。住み手である建主の夢に、プロとしての建築家のアドバイスが加わることで、期待以上の住まいが望めます。また、もうひとつの大きな魅力は、「逆転の発想」です。敷地が狭い、変形している、日当たりが悪い、などの困難な条件も、建築家の柔軟なアイディアによって、逆にメリットに変えることもできるのです。
これは、「予算が限られている」という悪条件についても同じことが言えます。お金をかけられないなら、それを逆手にとって、ローコストでも魅力的な住まいになるよう工夫してくれます。豪邸しか建ててもらえないのでは、なんて心配は無用なのです。条件が厳しいからこそ、建主と建築家が協力して、知恵を出し合う必要があるのです。
しかし、お互いの感性が合わないと、その共同作業がむずかしくなるのも事実です。設計やデザイン、住まいに対する考え方などが、自分に近いと感じられる建築家を、時間をかけて探すことがとても重要です。たとえ、断ったり断られたりの繰り返しになっても、納得のゆくパートナーに出会えるまで、妥協をしないことが大切なのです。それこそ「お見合い」をするくらいの気持ちで臨みましょう。ですから、家の完成を急ぐ人には、建築家や設計事務所はあまりおすすめできません。
建築家との家づくり
オリジナルで個性豊かなデザインの家が欲しい、ドアノブひとつにまで徹底的にこだわり抜きたいという方には建築家との家づくりが似合います。建築家との家づくりの最大の特徴は、あなたの細かな希望や要望を反映させた家づくひをしてくれることです。もちろんその力量にもよりますが、建築家はあなたの要望を聞き込みながら、自らの経験と建築に関する知識を盛り込んだプランを提示してくることでしょう。建築家は依頼してくる人のことを「お客様」とは呼びません。「クライアント」と呼びます。そしてあなたの要望を汲み取ってつくった家を「作品」と呼びます。つまりその立場は、あなたとまったく同等か、あるいはその上かもしれません。建築家=先生と呼ばれるゆえんです。
さて建築家との家づくりの注意点ですが、建築家の基本的な業務の範囲は設計です。一般的には施工監理も請け負うことになるので、あなたは建築家と「設計監理契約」を結ぶことになり、トータルに家づくりの面倒を見てくれることにはなりますが、施工自体は別の建設会社に委託することになります。業務形態と作風にも注意が必要です。建築家というのは自宅を事務所にしてひとりで設計業務を行なっているケースと、グループを組んで行なっているケース、大人数のスタッフを抱えているケースがあります。その作風も、無機質の材料を使うデザイン住宅が得意だったり、断熱材にわらを使ったストローペイルハウスなど、とことん自然素材の住宅にこだわる建築家がいたりとさまざまです。
ですから建築家との家づくりでは、まずその建築家の「作品」を見せてもらうことが大切です。建築家は個性的な感覚をもち、デザインなど主義主張を明確にもっている人が多いので、あなたとの「相性」がとても大事になります。
施工管理もしてくれる「建築家」
家を建てるときには、直接工務店や住宅メーカーに依頼する方法と、建築家に設計と施工監理を依頼する方法とがあります。建築家に依頼するには多少のコストがかかりますが、施工監理まで行なってくれるので、その分かなり安心感が高まります。
では、その設計・監理料はどれくらいかかるのかといえば、おおむね建築費の10%程度になるようです。知名度などによって多少変わることがありますが、一般的には2,000万円程度の建築費であればその20%ほどの240万円程度、3,000万円なら10%の300万円ほど、5,000万円なら8%の400万円ほどとみておけばいいのではないでしょうか。たしかに、その分コスト負担になるわけですが、建築家のなかには木材を産地から直接仕入れる、関係の深い工務店に何軒も発注することでコストを下げるといった形で、ローコスト住宅を実現している人もいます。設計・監理料を支払っても、工務店や住宅メーカーに直接依頼するより安く上がることがあります。
建築家の知り合いがいなくても、日本建築家協会や各地の支部などを通して紹介してもらうことができますし、公式ホームページでどんな物件を手がけているのかなどを調べて依頼することもできます。設計・施工を一括して工務店やハウスメーカーに依頼する場合には、通常は設計・監理料込みの見積もり、契約になります。グループ内や社内で設計、施工の各業務を分担するので、スケジュールは比較的スムーズに流れますが、反面、施工監理の目が馴れ合いになってしまう可能性がないとはいえません。チェックポイントをシッカリと確認した上で、自分でも足繁く工事現場を訪問して、チェックの目を光らせておくことを忘れないようにしたいところです。
施工会社の選び方のチェックポイント
- 経験者、知り合いなどに評判を確認する
- 継続した実績があるかどうかを確認する
- 最近建築した物件に関する実績集を見る
- 最近建築した物件の実物を見て、住み心地を聞く
- 工事見積書が細かく算出されているかを見る
- 支払い条件が明確になっているか確認する
- 手付金を出す場合には前金保証制度があるかを確認する
- 性能保証制度があるかどうかを確認する
- アフターサービスの有無を確認する
- 工事請負契約書の中身を確認して契約を結ぶ
依頼の仕方 【建築家・設計事務所】
住宅雑誌やインターネットが有効な情報源です。気になる実例を集めていくだけでも、自分好みの住まいや建築家の傾向がわかるでしょう。建築家の会やネットワークの情報をチェックして、セミナーなどに積極的に参加して、建築家の「生」の姿にふれてみるのもいいでしょう。また、最近増えてきた建主の希望を聞き、それに見合った建築家を紹介したり、問に立って話を進めたりする『コーディネーター』を利用する手もあります。
何人かの建築家が候補に挙がったら、直接アプローチをしましょう。そのとき、家づくりの動機や予算、どんな家にしたいのかなどをおおまかに話したり、事務所のシステムについて質問したりしてみましょう。どんな対応をしてくれるか、十分に確認しましょう。その後、日時を決めて、事務所を訪問します。より具体的な話をすることはもちろんですが、できれば雑談も楽しんでください。お互いの相性を知る、絶好のチャンスになります。ほかの実例を見せてもらったりしながら、ざっくばらんに話してみることをお勧めします。
設計・デザイン 【建築家・設計事務所】

ハウスメーカーや工務店の画一的な住宅にはない、個性的な設計・デザインが最大の魅力です。それも、けっして奇をてらうのではない、機能性や使い勝手に裏打ちされた提案をしてもらえます。「相手のセンスを押しつけられるのでは」と不安に感じるなら、その建築家の実例をいくつも見て、比較してみること。一軒一軒、違う工夫がなされているようなら、それぞれの住み手の希望がとり入れられている証拠です。
さらには「自分なりのイメージをうまく伝えられない」という人は、参考になる写真などを持参しましょう。ただ「こんな家を」というのではなく、具体的にどの部分をとり入れたいのかを、気負わずに話してみましょう。また、ライフスタイルについて伝えるためには、今住んでいる家に招いて、実際の暮らしぶりを見てもらうことをお勧めします。実はこの方法は非常に効果的なイメージ伝達方法なのです。恥ずかしがらずに、家族それぞれの生活や、持ち物の量などをチェックしてもらいましょう。
建築コスト 【建築家・設計事務所】
予算の監理も建築家の重要な仕事です。金額の大小にかかわらず、はじめにはっきり予算を伝えておけば、そのなかでできる最良のプランを提案してくれるはずです。以外にも「ローコスト住宅は腕の見せどころ」という建築家もいるほどです。素材や設備の質を落とすのではなく、設計プランをシンプルにしたり、工事の科目数を減らしたりして、コストを下げるよう工夫してくれます。とはいえ、建築家によって、手がける家のグレードはさまざまです。これまでの実例の建築費や坪単価などを調べて、どの程度の予算の家が最も得意な建築家なのか、早めに見当をつけておくことは必須と言えるでしょう。
建築家に支払う設計料は、工事費の1~2割前後が一般的と言われています。このなかには、プランづくりのほか、敷地の調査や竣工までの設計監理、建築確認申請などの法的な手続き、工務店と施主の調整など、さまざまな仕事が含まれています。パートナーとして、プロデューサーとして奔走する報酬として考えると工事費の1~2割は、妥当と言えるでしょう。
施工・施工監理 【建築家・設計事務所】
施工業者を選ぶときの建築家の役割は、あくまでもアドバイザーとなります。業者の候補をあげ、相見積もりなどを慎重に比較検討し、必要なアドバイスをしてくれますが、工事契約をするのは、建主自身、施主自身です。施工業者の信頼度を測るという大役は、自分の責任で果たすことになります。
実際の工事が始まると、建築家は現場に足を運んで、設計どおりに進んでいるかどうか、施工の状態や日程などを厳しくチェックしてくれます。工事中の現場を、第三者の立場から、プロの目を通して見てもらえることは、建築家に依頼する大きなメリットです。ハウスメーカーや工務店に依頼した場合は、この立場の人がいないので、トラブル処理などは自分で行うことになります。ここは大きなポイントです。
また、現場には、工事のじゃまにならない程度に、自分たちも見学に出かけましょう。工事の様子を写真に撮っておけば、家づくりの記念になり、将来リフォームなどをするときにも役立ちます。しかし、現場で直接、変更などの指示をするのは禁物。必ず建築家を通して行いましょう。
アフターケア 【建築家・設計事務所】
一般的に引き渡しのときに、建材や設備の手入れの仕方などについて、説明を受けることになります。入居して1~2年の間は、なにかと不具合が生じるものです。その場合の応急処置法や、メンテナンスしてくれる業者の連絡先、さらに5年後、10年後に住まいのどんなところをチェックすればいいかなどを、くわしく聞いておきましょう。
建築家によっては、定期的に様子を見に訪問してくれるサービスを行っているところが増えてきています。いずれにしろ、住み始めてからも長くおつきあいできる、親しい関係を築いておくのがベストと言えるでしょう。また、取り越し苦労と思われても、どんなアフターケアをしてもらえるのか、契約の前に確認しておくことが大切です。
★資格がなくても建築士にはなれる!!
「建築家」と「建築士」の違い
「建築士」と似た言葉に「建築家」というものがあります。分かりやすくするために、
建築家と建築士の違いをまとめてみましょう。
●建築士
建築士の試験に合格して登録をした人の事です。設計・監理の資格はありますが、有資格者全員が充分な設計監理能力をもっているわけではありません。設計事務所勤務者はもちろんですが、施工管理者、建材営業マン、各工種施工主任、学校の先生、設計・監理の実務経験ほとんどなしの建設業営業マン、主婦、不動産屋さん、建築行政マンなども、建前上建築士として登録していることがあります。
●建築家
職能を意識し、建築設計に高い志と倫理観をもち、文化教養を兼ね備え、良心的に建築活動をする人が建築家と言えるでしょう。ただし、芸術家気取り、デザイナー気取りの建築家、高慢な建築家、高飛車な建築家、若く流行に敏感で派手好みの建築家など、機能や維持管理を忘れて、人の金で自分の作品をつくる輩もいるので注意が必要です。実は、建築家のなかには、建築士の資格をもっていない方もまれにいます。有名な料理研究家でも調理師免許を持っていない人もいます。つまり、「建築士」は法律上の資格、「建築家」は職業名、というわけです。建築家には、建築士の免許を持っているかの確認をするべきでしょう。
設計事務所は規模で選ぶな!!
みなさんは注文住宅を建てるなら、「大きい設計事務所なら安心」とお考えになるでしょうが、しかし、大きな事務所は、大きな建物や公共建築を設計しているところがほとんどです。個人住宅の設計は片手間にされている場合もあるので、しっかりと調べる必要があります。大手でも、個人住宅の場合は、実際にはひとりないしふたりが担当となるのが普通ですから、事務所に何十人と設計士がいても、全員が対応するわけではないのです。短時間で設計する場合は、人を集めやすい大手事務所のほうが有利ですが、設計期間を無理に縮めようとするのでなければ、大きな事務所と小さな事務所の差はないと考えていいでしょう。
「建築家」「設計事務所」との家づくりのコストダウン
コストダウンで一番大切なのはコストのかけ方です。こだわるところと切り捨てるところを明確にしましょう。慎重に検討してバランスをとれば、ムダがなく使いがっての良い家ができるはずです。建築家を選ぶなら信頼し合える関係づくりがコストダウンンにつながります。

コストダウンやローコスト住宅も「建築家」の専門分野!!
建築家というと、ビルや豪邸ばかりを手がける、いわゆる「先生」を想像するかたも多いのではないでしょうか。実際には、建築家の多くは予算内で希望をかなえるために、知恵をしぼってくれる人がたくさんいます。なかには「ローコスト住宅こそ腕の見せどころ」という建築家もいるほどです。プランニング、素材や設備選び、施工など、すべての段階であなたに合った、コストダウンのアイディアを出してもらえるはずです。
建築家との家づくりは、いわばオーダーメイドと言えるでしょう。間取りからデザイン、細部までこだわって、オリジナルの家をつくれるのが大きな魅力です。そこで大切なのが、パートナーとしての相性です。センスや価値観が近い人を選ぶことが、家づくり成功の重要なカギになります。家への希望はもちろんのこと、ライフスタイルなどについても理解し合えれば、コストのかけどころ、削りどころについても、ツボを押さえた最適なアドバイスが期待できるでしょう。
※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。