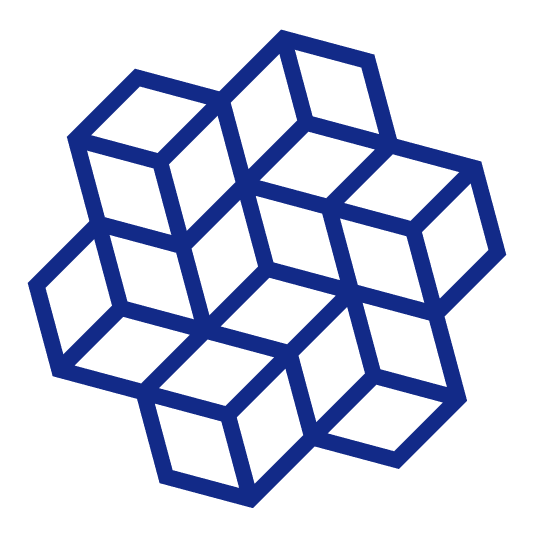【残念】ZEH住宅の補助金が55万円に減額!!【2022年】
令和4年度のZEH住宅の補助金は55万円
平成29年度 ZEH住宅の補助金は『75万円』!!
令和4年度・2022年度のZEH住宅の補助金は55万円となりました。
とても残念なことに前年28年度から40%もの大幅減となってしいました。一部には増額との噂も出ていましたが、結果としてはZEH住宅検討者にとっては大きな痛手となる結果となりました。50万円の減額ですので、ちょうど標準的な蓄電池システムの本体価格と同等です。国が目論むZEH住宅の普及には大きな足かせとなるのではないでしょうか?
◆令和4年度(2022年度) ZEH住宅の補助金:55万円
【うっそ~減額】 蓄電システムの補助金も減額!!

ZEH住宅の補助金は大きな減額となりました。ZEH住宅の検討者にとっては大きな痛手です。実はそればかりではありません。ZEHの補助金対象となる住宅には、蓄電システムを導入した場合に個別に補助金が支給されます。しかしこの蓄電池システムの補助金も減額となりました。本年度令和4年度の蓄電容量1kwh当たりに対して4万円に変更になりました。令和3年度(2021年度)が1kwh当たりに対して5万円の補助金でしたので、1万円の減額となりました。
ZEH住宅の補助金、蓄電システムの補助金・・・・ともに大きな減額です。ZEH住宅をご検討させる方にとっては頭の痛い話です。しかし、悪い話だけではありません。実は木造住宅やローコスト住宅でZEHをご検討させれる方にとっては朗報もあるのです。
ZEH補助金の審査基準の緩和! ローコストにもチャンス?
補助金に関してはネガティブな情報ばかりですが、実は木造住宅やローコスト住宅には朗報もあるのです。本年度は補助金の減額だけではなく、その審査基準の緩和があるのです。ある特定の住宅にはこれまでよりも有利な補助金審査が行われるのです。
◆審査の変更点

補助金の審査は、一部では緩やかな方向へとかわりました。昨年度までは大きな費用をかけたZEH住宅のほうが、審査に受かりやすい側面がありましたが、それがZEH住宅の高騰に拍車をかけているという批判もあがっていました。ですから、本年度より外皮および設備機器の価格の上限を設定することとなります。これまでは明らかに大手ハウスメーカーの高額なZEH住宅のほうが、補助金審査に通りやすかったのですが、価格の上限設定により一般的な価格のZEH住宅や、ローコスト系のZEH住宅にも門戸が広がる可能性が大きいのです。この変更はZEH住宅=高額な住宅というイメージが覆される変更かもしれません。
ネットでZEH住宅の『見積もり』請求ができます!!
●積水ハウス
●ダイワハウス
●セキスイハイム
●三井ホーム
●パナホーム
●ミサワホーム
●トヨタホーム
●タマホーム
●アキュラホーム
●アイフルホーム
などなど・・・・・・・・・
ZEH住宅はどこのハウスメーカーが良いのか?

ZEH住宅を建てるなら、どこのハウスメーカーが良いのでしょうか?
ZEH住宅はハウスメーカーによって、得意・不得意の差がはっきりしていると言われています。それが価格や仕様にはっきりと出るのが現実です。全く同じ仕様で建てても、総額が大きく変わって来るのです。
個人的には、一つの指針としてこれまでの実績をもとに判断するのが良いと思っています。その助けになるのが「ZEH住宅の普及実績」です。平成28年度のZEH住宅の補助金受給実績が発表されています。このデーターを見れば、どのハウスメーカーが得意なのか?あるいはそうでないのか?の判断がつくはずです。ここでは多くを語りませんが、現状ではZEH住宅の分野においては、その差は明白です。恐ろしいほどの差がついているのが実情です。今後IoT住宅への発展が期待されますが、ここに名前が出ていないハウスメーカーの奮起に期待します。
| 積水ハウス | 74% |
| 一条工務店 | 54% |
| セキスイハイム | 32% |
| 日本ハウスHD | 24% |
| ダイワハウス | 22% |
| パナソニック ホームズ | 17% |
| ミサワホーム | 15% |
| スウェーデンハウス | 14% |
| へーベルハウス | 12% |
| 三菱地所ホーム | 9% |
| 三井ホーム | 7% |
| トヨタホーム | 7% |
| アキュラホーム | 4% |
| タマホーム | 1% |
エコ住宅・ZEH住宅の補助金は凄い!!
太陽光発電補助金申請は40万件を超える!!
エコ住宅やZEH住宅を建てたり、買ったり、また既存の住宅にエコ関連・ZEH関連機器を設置するときなどには、各種の補助金を有効に活用しましょう。機器によっては、国だけでなく、都道府県や市区町村にも補助金制度があり、あわせて利用できることが少なくありません。
補助金の対象となっている機器を設置するときには、住宅や機器のメーカー担当者が教えてくれるはずですが、あらかじめ補助金制度を知っておけば、資金計画などを立てやすくなるはずです。こうした補助金制度が大きなインセンティブとなっていることは間違いありません。たとえば、太 陽光発電システムに関してみてい くと、2008年度に補助金制度 がスタートしてから、急速に設置 件数が増加しています。当初は年 間2万件だったのが11年度、12年度と30万件を超えるレベルに 達 しているのです。 このうち半数が新築住宅とすれ ば、年間の新設住宅着工戸数は100万戸台ですから、5戸に上戸程度 は太陽光発電システムを搭載した 住宅になっている計算。現実的に は一戸建てが中心でしょうから、一戸建てだけでみれば、割合はも っと多いはずです。では、図表を参照しながら、各種補助金について、国の制度を中 心にみていきましょう。太陽光発電システムの補助金額は、設置する機器の価格が2万円 超41万円以下であれば、1kW 当たり2万円で、41万円超50万 円以下が1万5000円です。上限は19万9800円となっています。
2021年度の制度ではlkW当た り 3.5万円でしたから、かなり減 っていますが、これはシステムの 設置費用が年々安くなっているこ とに対応したもの。太陽光発電シ ステムで発電した電気のうち、家 庭内で使い切れない電気を、電力 会社が買い取ってくれる余剰電力 の買取制度もありますから、設置 後10年間で設置費用を回収でき る 点はほぼ変わりがありません。
家庭用蓄電池は 1台当たり100万円の時代もあった
エネルギーをつくり出す創エネ 機器としては、都市ガスを利用し た燃料電池もあります。こちらは、設置機器の価格から 23万円を控除した金額の2分の1に、工事費の2分のIを加えた金 額が補助され、上限は45万円と な っています。 さらに、太陽光発電などでつくもあり、こちらは機器費用の3分のまで上限が100万円と、大型の補助か実施されています。このほか、家庭内のエネルギー消費を管理・制御する家庭用エネルギー管理システム(HEMS)についても、定額10万円の補助金があります。住まいの省エネを進めるためには、自らエネルギーをつくり出し、それを貯め、有効活用することが大切といわれますが、それぞれに関わる機器への補助金がそろったことになります。
国の制度だけではなく、自治体でもさまざまな補助金制度を実施しています。なかには、太陽光発電については1kW当たり20万円、上限60万円というように、国よりも充実した制度を実施しているところもあります。居住地の都道府県、市区町村の情報を調べて、制度がある場合には確実に活用するようにしましょう。これらの機器を設置すると、初期費用は高くなりますが、それでも補助金をフルに活用すれば、かなりの部分をカバーできますし、設置後は光飲薪の負担が大幅に軽減されます。省エネ機器を設置した住宅は、地球にやさしいのはいうまでもありませんが、長い目でみれば、家計にもやさしい住まいということができます。
※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。