

注文住宅を建てる時のチェックポイント【建築前~建築後】

せっかくの夢のマイホームも後々欠陥がわかっては、いくら後悔してもしきれません。安心で快適な一戸建て住宅を手に入れるためには、「建築前」、「建築途中」、「完成後」と、それぞれの段階でチェックすべきポイントがあるのです。しっかり身につけて、欠陥や手抜きからあなたの家を守りましょう。
建築前に確認すること

地盤の強さや地質を理解しよう
「地盤」とは、建物を支える地表付近のことです。特に、建物を建てるとき、その荷重を基礎部分で受け、支えることができる地盤を「支持地盤」といいます。
具体的に建物を建てることになったら、その敷地がどれくらいの重さまで耐えられるかという「地耐力」が問題になります。一戸建て住宅の場合、地表から5mくらいの深さまでに柔らかい地層がないかどうかがポイントです。その範囲での地耐力が1㎡当たり3トンあれば、比較的良好な地盤と考えられます。建築に着手する前に、地盤調査は必ず行ないましょう。法律には、地盤の強さに応じた基礎を選ぶよう明記されているため、事実上、一戸建て住宅でも地盤調査は義務化されています。
実際の地盤調査は、一戸建て住宅の場合、「スウェーデン式サウンディング試験」という方法で行なうのが一般的です。これは、先端にスクリューが付いた鉄製の棒におもりをのせ、人が手で回転させながら地面に突き刺していき、おもりの重量や回転数、手の感触などをもとに地質や地耐力を調べる方法です。同じ敷地内でも少し離れると地層が変化していることがあるため、建物の四隅にあたる場所を調べるのが基本です。装置が小さく、費用も1件当たり数万円といったところです。地盤調査の結果、もし地盤が弱い場合には、杭を打ったり、地盤を改良したり、基礎の補強工事をして、地盤を強化することが必要になります。
隣地との境界をしっかりと確認
地盤調査とともに重要なのが、境界の確認です。昔からの住宅地では、境界が不明になっている所が少なくありません。境界杭は、コンクリート製で赤く十字が刻まれているものが一般的です。そのほか、コンクリート製で矢印になっているものや、道路側溝の上に金属のプレートで矢印になっているものなどもあります。
境界がはっきりしない場合は、周囲の土地所有者全員が立ち会って、境界を両定することが必要になります。所有者の都合が合わず、画定に何日もかかることも決して珍しくありません。ですから、境界画定は、できるだけ早めに行なうようにしたいものです。また、両定したらきちんと境界杭を入れて、誰が見てもはっきりとわかるような形にしておきましょう。現在は隣地所有者との関係が良いからと口頭で合意するだけだと、将来トラブルに発展する懸念もあるからです。
ライフラインで建築費用が大きく変わる
【上水道】
上水道は、本管からの引き込みの有無や引き込み管の口径によって、付帯工事の費用が大きく異なります。引き込みの有無は、敷地内に水道のメーターボックスや引き込み位置の目印となる杭があるかどうかで確認しましょう。前面道路の本管から新たに引き込むとなると、自治体にもよりますが、おおむね80~100万円以上の工事費がかかってしまいます。引き込み管の口径で多いのは、13mm、20mm、25mmの3種類です。古い住宅地では13mmが多いのですが、最近の一戸建てはこの口径では不十分。一般家庭でも20mm、2世帯住宅なら25mmに取り替える必要があります。もし、現地で引き込み管の口径がわからない場合は、水道局に問い合わせれば教えてもらえます。
【下水道】
排水の処理方法には、大きぐ分けて下水道と浄化梢の2種類があります。道路に下水道がない場合は、敷地内に浄化梢を設ける必要があります。下求道の有無は、道路にマンホールがあるかどうかでわかります。現在は下求道が通っていなくても、数年後に整備されることもあるので、地元の市役所などで下水道の整備計画を確認しておくとよいでしょう。
浄化槽を設ける場合は、汚水と雑排水を一緒に処理する合併浄化槽なら、1家族4名用で約100万円前後の費用がかかります。浄化槽が必要なエリアでは、土地の価格にあらかじめこの費用も加えて検討しておきましょう。また、以前浄化槽を使っていて下水道が通ったエリアでは、敷地内にまだ浄化槽が埋まっていることも考えられます。この場合、新しく家を建てる際に除去する必要があります。
【ガス】
敷地の前面道路に都市ガスの本管が通っていれば、都市ガスが利用できます。都市ガスが来ていない地域では、プロパンガスを利用することになります。プロパンガスエリアもまだ意外に多く残っています。引き込みの位置は、杭や道路のマークで確認します。引き込み管の端には通常、プラスチック製の杭があるため、簡単にみつけられるでしょう。現地に杭がない場合は、道路にGのマークやステッカーがあるかどうかをチェックしましょう。そこに引き込み管が埋まっています。ガスの引き込み工事はガス会社が行ない、費用は、敷地内にあるメーターまでがガス会社の負担、そこから先が利用者の負担となります。
建築中はここをチェックしましょう!!

図面をもらって現場で確認しよう
いよいよ建物を建てる段階に入ったら、ぜひ現場へ足を運んでみましょう。業者まかせにせず、自分でもチェックをすることは、とても重要です。現場の職人さんと顔見知りになれば、いろいろと教えてもらえることもあるでしょう。何より、マイホーム建築のプロセスを一緒に味わえることこそ、一戸建てを建てる醍醐味なのです。ただし、自分で現場をチェックするためには、工事用の図面が必要です。基礎伏図、床伏図、矩計図といった詳細な図面まで、事前に必ず受け取っておきましょう。これらの図面は、将来のメンテナンスやリフォームの際にも必要になります。
基礎工事ではここをチェック
【配筋】
建物の耐久性を左右するのが基礎工事です。ここでまず、設計図に沿って鉄筋を配置する「配筋」を行ないます。「配筋」は、施工会社の社内検査や第三者検査などでほとんどの場合、チェック項目に入っている重要な工程です。「配筋」時によくある問題は、コンクリートの厚み不足です。通常、コンクリートの中には鉄筋が入っていて、この鉄筋を包み込むコンクリートの厚みを「かぶり厚」といいます。この「かぶり厚」が厚いほど、コンクリートの中性化か鉄筋に達するまで年数がかかり、寿命が長くなります。
一般的に、中性化か進むのは10年で1mといわれており、「かぶり厚」1mの違いで、耐久性が10年違ってくるわけです。建築基準法では、「かぶり厚」を基礎の立ち上がりで4m、その他の基礎部分では6mと規定しています。現場では、「かぶり厚」を確保するために、型枠と鉄筋の間に、スペーサーという部材を挟み込みます。もし、このスペーサーがなかったり、数が少ない場合は、かぶり厚が確保されない恐れがあるので要注意です。現場をひと通り見て、鉄筋と型枠のすき間が狭そうな所があれば、実際にメジャーで測ってチェックしましょう。もし厚みが足りなかったら、規定通りに直してもらう必要があります。
【コンクリート打設】
型枠にコンクリートを流し込むのが「コンクリート打設」といわれる工程です。この作業がきちんと行なわれるかどうかも、基礎の鉄筋コンクリートの仕上が昨を大きく左右します。
チェックするポイントの一つは、加振機の使用です。コンクリートは、水とセメント、砂、砂利などを混ぜてつくられます。そのため、すき間が狭い所などには、コンクリートが十分まわらない恐れがあります。そこで、加振機を使ってコンクリートに振動を与え、隅々まで行き渡らせるのです。作業人数が少ないときなど省かれるケースがあるので、きちんと行なわれているか確認しましょう。もう一つのポイントは、コンクリートの打設時間です。コンクリートは調合後、すぐに固まりはじめるため、ミキサー車がコンクリートエ場を出発してから一定以上の時間が過ぎると、かなり品質が落ちてしまいます。品質を守るための基準は、気温が25度以上なら90分以内、以下なら150分以内と定められています。つまI冬なら2時間、夏なら1時間半以内です。出発時刻は、コンクリートの納品書に必ず記載されています。ミキサー車の到着が渋滞などによって大幅に遅れて固まりはじめている場合などは、そのままミキサー車を返す判断も必要になります。
また、コンクリートの調合は非常に微妙で、水分が増えるとコンクリートの質の低下につながります。したがって、流し込みの途中で水を加えたりすることはもちろんあってはなりませんし、雨の日に打設を行なうのも避けるべきです。
本体工事ではここをチェック
【骨組み】
土台や柱、梁といった建物の骨組み部分では、配管や配線などを通すために大きな穴を開けたり、欠き込みがされていないかを確認しましょう。設計上は必要な強度を満たしていても、実際の工事でそういった不良個所があると、本来の強度が発揮されなくなってしまうのです。もし大きな欠き込みを発見したら、可能な限り材料を新しいものに替えてもらいましょう。それができないなら、少なくとも何らかの補強をしてもらうことが必要です。もっとも、むしろ大切なのは、そういった欠き込みを防ぐためにあらかじめ、設計段階で配管などを通す空間を確保しておくことです。前もって確認しておくことが大切になります。
【金物】
柱や梁などの構造材をしっかりつなぎ、耐震性をアップさせるのが金物です。業者から金物の取り付け位置を記載した図而をもらい、取り付け状態を確認してみましょう。特に重要なのは、筋かいと柱や土台をつなぐ「筋かいプレート」です。取り付け方法やビスの必要本数は金物によって異なりますが、ビスが奥までしっかり入っていることは必須です。もう一つ重要なのが、柱と土台などをつなぐ「ホールダウン金物」です。これは、金物が柱から離れすぎていないかをチェックしましょう。あまり離れていると十分な効果が得られないので、写真のような「ジョイント金物」で補修する必要が出てきます。
【断熱】
省エネや快適性に欠かせないのが断熱ですが、期待通りの断熱性能実現のためには、断熱材のていねいな施工が不可欠です。一戸建て住宅で最もよく使用される断熱材は、ガラスを原料にした繊維状のグラスウールです。チェックポイントとしては、グラスウールの厚みが仕様書と同じか、またホルムアルデヒド対策等級の星の数がいくつかを確認します。現在、ホルムアルデヒド対策は、最上級の4つ星が常識です。
グラスウールは、壁や天井など必要箇所にすき間なぐ敷き詰められていなければ、想定の断熱性能が発揮されません。さらに、本体を入れた包装の耳の部分を間柱の所で張―合わせ、包装がつながって気密層ができるようにする必要があります。断熱は非常に重要な工程ですが、用いる断熱材の種類によって施工方法が異なるなど、確認が難しいポイントでもあります。適切な断熱性能を確保し、快適で長もちする建物をつくるためには、専門家にチェックを依頼するのも有効でしょう。
【防水】
雨漏りは、建物のトラブルで最も多いものです。これを防ぐには、屋根や外壁の下地に防水紙をきちんと張っておくことが重要です。張ひ方の基本は、下のほうから順に横張りにすることです。上から張ったり、縦張りにしたりすると、雨が強く降ったときに張ひ合わせのすき間から雨水が中に入り込んでしまう恐れがあるからです。防水紙には通常、上下方向の重ね幅を示す線が印刷してあります。その線まで防水紙を重ねて、重ね幅が確保されているかチェックしましょう。また、防水紙をとめるステープルの周辺に大きな破れがないか、ステープルの間隔が広すぎないかの確認も必要です。
建築後はここを確認しよう!
内覧会で隅々までチェック
内覧会は、念願のマイホームとはじめて対面できる完成お披露目会です。同時に、購入者による自主検査といケ非常に重要な意味ももっています。内覧会で建物を確認したといケ意味の書類にサインしたあとは、基本的に、表からすぐ気がつくような不具合があっても、売主に責任を問うことは難しくなります。また「アフターサービス」の対象になるとしても、入居後に大がかりな補修工事を行なうのは、日常生活に大きな支障をきたすでしょう。本来は、内覧会の前に業者側がしっかりとした検査を行なうべきなのですが、残念ながら検査に疑問を感じるほど、仕上がりにバラツキが多いという現状があります。建物はあくまで手づくりであるため、現場を担当する監督や職人の技量に大きく左右されてしまうのです。
また、内覧会までに完成しているのが建物本体だけで、門扉などの外構工事や造園工事が完了していないケースもあります。そんな場合は、すべての工事完了後に内覧会を行なえるよう、依頼しておくようにしましょう。内覧会は、残代金を支払う前に行なう物件チェックの最終関門です。しっかり冷静に、納得できるまで確認を行ないましょう。
内覧会での確認ポイント
【建物の外側】
内覧会の当日、まず建物の中に入る前に、周辺でチェックしておきたいことがあります。
①外壁・基礎
②屋根
③外構
④境界
①〜③はいずれも、全体的に目視して、ひどい汚れやキズ、ひび割れといった欠陥がないかを確認します。低倍率の双眼鏡があると便利でしょう。同時に、図面や仕様書との相違点がないかも確認しておきましょう。④の境界は、工事中に境界杭がなくなったり、壊れてしまったりするヶIスがあるため、再度確認しておく必要があるのです。
【床、床下】
建物の中に入ったら、各部屋の床からチェックしましょう。部屋の隅から隅までを、体重をかけて踏みしめてみて、異音が発生する簡所がないかを確認します。もし、床鳴りのする筒所があれば、下地や床組みの調整が必要になります。
次に、ホームセンターなどで2000円前後で入手できる水平器を使って、壁際や家具を設置する予定の箇所の床の傾きを測ります。建物は工業製品ではないので、床の仕上がり精度に多少の誤差があっても、一定範囲内なら問題はありません。水平器によって目盛が異なるため一概にはいえませんが、微妙に振れている程度なら問題ないレベルといえるでしょう。床のヘコミやキズなどは、個人的な感覚も大きいもの。引越しや入居後、いずれはついてしまうような小さなキズなどにまで、あまり神経質になる必要はないでしょう。キッチンの床下収納や洗面室の点検囗からは、床下が確認できます。懐中電灯で照らしてみて、もし床下が異常に湿っていたり、木片などが多数見えるようなら、現場担当者に指摘して確認してもらいましょう。
【建具】
木質系のドアや収納部の扉は、工場生産品が多いため、比較的高い精度があります。しかし、枠の部分は現場で組み立てるため、誤差が生じる場合があります。施工誤差が調整可能な範囲を超えていると、ドアや引戸の開閉で枠と建具が干渉して、動作不艮を起こしてしまいます。家じゅうのドアをすべて開閉させてみて、不自然な感じがないかをよぐ確認しましょう。
内覧会で不具合があったら
内覧会が終わると、不具合を指摘した箇所を一つずつ現場担当者と見てまわり、補修方法について確認します。それらがきちんと直っているかどうかは、再内覧会で確認します。仕上がりに納得がいくまでや昨才直してもらうのは、買主、施主の権利ですが、あくまで常識の範囲内で行なうようにしましょう。また、不具合があっても、感情的になったり、強引に解約や値引きの交渉をするのではなく、冷静に補修や調整の依頼をすることが大切です。不動産会社や建設会社とは、入居後も長い付き合いが続くことをふまえて、落ち着いて信頼関係を築き、納得できる内覧会にしたいものです。
キッチンのプランニングに迷ったら 【注文住宅の間取りの悩み】
専門家を利用するなら
一戸建て住宅は個別性が高く、施工精度に大きなバラツキがあるのが現状です。そのため、たとえしっかりした設計がされていても、図面通りに施工されなければ、耐久性も快適性も大幅に落ちてしまいます。よリ安心で快適なマイホームづくりのためには、専門知識をもったプロにホームインスペクション(住宅診断)を依頼するのも有効な方法です。これは、建築のどの段階のチェックにおいてもいえることです。ホームインスペクターは、建物を診断した実績が多く、当事者の利害にとらわれない第三者性を堅持していることが重要です。信頼できるホームインスペクターを探しましょう。
※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。
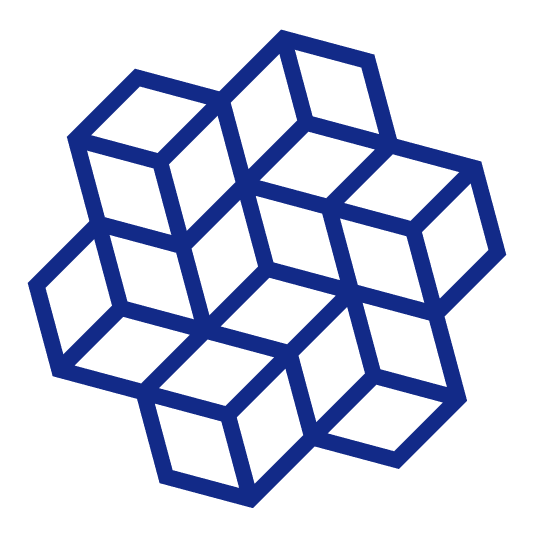





.jpg)



.jpg)