

定期借地権でマイホームを建てても大丈夫?!

「定期借地権」 理解していますか?
借地によるマイホーム計画は、土地代が大幅に安くなる利点があります。それを可能とした「定期借地権」住宅は、各社の戦略商品になってきました。
定期借地権は1992年8月に施行された新借地借家法により登場しました。「借地貸す馬鹿、返す馬鹿」といわれてきたように旧法では借地人の権利が強すぎて、地主側の借地供給が先細りとなる弊害がありました。新法では、半永久的に土地が地主に返還されないような規定を改め、地主サイドの権利の強化を打ち出しています。その新法の中核的存在が定期借地権です。定期借地権とは、その名のとおり一定の借地契約期問が満了すると法的に消滅する借地権で、法定更新もなく確実に借地関係が終了します。
「定期借地権」とは?
定期借地権(略して定借)というのは、期間を主に50年と定め、その期間だけ土地を賃借するという制度です。 50年後には、必ず地主に返さなければなりません。土地代が要らない代わりに、月々の地代は払わなければならず、保証金として土地代の15~30%ほどを預ける必要もあります。この保証金の額は、大体、将来の解体費に準じて決められるのが一般的です。土地の返還に際しては、建物を解体し、更地で返す必要があり、解体費と毎月の地代で、総額1000万円~数千万円の経費が必要となるため、あまり普及していないのが現実です。
定期借地権には用途や借地期間などによって3つの類型があります。そのうち、住宅供給に活用されているのが一般定期借地権で、住宅メーカーが先鞭をつけたのに続いて、最近ではマンション市場でも定期借地権付き分譲住宅の販売が活発化しています。定期借地権付き分譲方式(定借方式)のしくみは、簡単に説明すると、住宅メーカーなどの事業者が土地所有者と定期借地権契約を結び、事業者が借地の上に住宅を建設、住宅購入者が定期借地権を譲り受けて住宅を取得する、というものです。土地について購入者が支払うのは、当初の保証金と毎月の地代ですが、首都圏の場合、保証金は500万~1200万円、地代は2万~3万円台が平均となっています。定期借地権のおかげで、一般的な所有権分譲より40~60%割安な価格で住宅を収得できるようになりました。
「定期借地権」の6つの特徴!!
【PR】 タウンライフ
「土地購入」と「定期借地権」どちらが得か?
●土地購入の場合
ある地方都市の物件でシミュレーションしてみましょう。坪40万円の土地50坪(2000万円)に、仮に消費税込み1500万円の家を建てるとします。総額3500万円で、自己資金500万円、残りの3000万円は30年ローンで借りるとします。金利を2%とすると、利息が約1200万円ほどになります。土地にかかる固定資産税は、県や市によって違いますが、仮に年間約2万5000円ほどとすると、50年で125万円になります。すべてを合わせると、4825万円支払うことになります。
●定期借地権の場合
土地に対しては、保証金(解体費)として300万円、毎月の地代2万円が、50年で1200万円、合わせて1500万円の経費が必要になります。自己資金800万円のうち300万円を保証金に充てると、残りは500万円となります。家を2000万円となるので、住宅ローンは1500万円になります。 30年3%の利率とすると、利息が800万円ほどになります。 50年で総額、4300万円を払うことになります。
将来性でみれば土地購入のほうがお得!!
●土地購入の場合
家と土地の両方が自分のものになり、その後は安泰です。そのまま住み続けられますし、売るにしても、少なくとも土地の購入金額である2000万円が通常は物価上昇にリンクしますので、もっと高い資産が残ることになります。
●定期借地権の場合
土地を買う場合と比べると、支払うお金は1480万円ほど少なくて済みますのでラクです。しかし、50年後には返還しなければならないので、住む家を失い、財産も残らないという不安があります。また、買い取ったり、延長できるものもあります。
1480万円を払えるかどうかが分かれ目
簡単に言うと、土地購入の場合は、1480万円多く払って、老後住む家を確保し、最低2000万円の財産を残す、ということです。一方、定信は、1480万円を払わない代わりに、50年後には、住む家の心配をしなければならないというリスクを背負うということです。しかし、リスクはあるとはいうものの、「一戸建て購入が難しい低予算の人でも、一戸建てに住むことが可能」というのがこの「定借」の意義であると言えます。
定期借地権方式のメリット
定期借地権方式による住宅は、土地代が少ない分、建物に資金をかけることができ、よりグレードの高い住宅取得を可能としています。定借方式の販売物件の人気は高く、参入企業が相次ぎ、ちょっとしたブームを引き起こしました。その要因は、土地所有者、住宅購入者、事業者にとってご二方良し”のメリットがある点にあります。三者のメリットをそれぞれ簡単に説明すると、次のようになります。
土地所有者のメリット
①土地保有志向を充足=従来の借地権では一度土地を貸すと返還を求めることがきわめて困難で、多額の立退料を要求される例が多くありました。定借方式では契約期間の終了後、契約更新ができないため、確実に土地保有者に返還されます。
②事業リスクが小さい土地活用方式Hアパートなどの賃貸住宅や駐車場経営などの場合、事業資金の投入、管理・運営業務が必要となりますが、定借方式では経営上のリスクが小さく、管理などの煩わしさもありません。
③安定的な収入を確保=契約時に保証金などの一時金の確保ができるほか、その後は毎月安定した地代収入を得ることができます。
ユーザーのメリット
①居住コストが大幅に軽減=契約時には保証金などの一時金が必要となりますが、その額は土地購入費の20%見当であり、住宅購入時の負担が大幅に軽減されます。地代も周辺のマンションの管理費プラス駐車場代程度で、50年以上にわたる居住コストが大幅に軽減されます。
②良質で好みに合った住宅の取得が可能=借家と異なり、自分の好みに合った住宅を取得することができるうえ、購入価格が安い分だけよりグレードが高く広い住宅を取得することが可能となります。また、増改築も自由なため、ライフサイクルの変化に対応した住生活を実現することができます。
事業者のメリット
①土地投資関連のリスクの解消=土地を購入、造成して分譲する場合の投資負担、開発リスクがありません。これは、上物(建物)の販売増に結びつきます。
②潜在需要の掘り起こしが可能=マイホーム取得を諦めていた潜在需要者層の掘り起こしが可能です。
●利用されない定期借地権の現実!!
定期借地権を利用すれば、土地を購入して家を建てる場合にくらべ、総費用は約半分で済むといわれています。費用が半額になるなら、興味エお持つ方が多いのではないでしょうか。しかし意外と、この定期借地権が伸び悩んでいます。いえ、予想に反してかなり停滞しています。みなさんが身近に感じないのも無理はありません。
実は、ここには現在の社会的な背景があります。ご存知の通り平成不況のなか、銀行は不良債権にあえいで統廃合を繰り返しています。しかし、銀行の体質は依然、従来のシステム、つまり担保至上主義から抜け出せていないのです。例えば、あなたが定期借地権で住宅を建てようとします。通常は住宅金融公庫を使う人が多いと思いますが、驚いたことに、公庫は定期借地権では中間支払いはしません。建築が終わり、役所の検査の合格が終了したあとに全額が支払われます。工事費の施工会社への支払いは1/4分割が通常ですので、最後にまとめて支払うことを許してくれる業者は少ないと思えます。
このような状況でしたら、多くの方が次に考えるのは銀行の融資でしょう。しかし、先に記述しましたように、担保至上主義では、これに応じる銀行は大変少ないのが現状です。融資する銀行では「私どもが選定した「ウスメーカーの、いずれかで建築するのなら中間融資いたします」という条件が付くのです。このように「定期借地権は大変不自由」というのが実状なのです。今後の政策に期待したいものです。
※記事内には「PR」の宣伝活動および、アフィリエイト広告が含まれております。
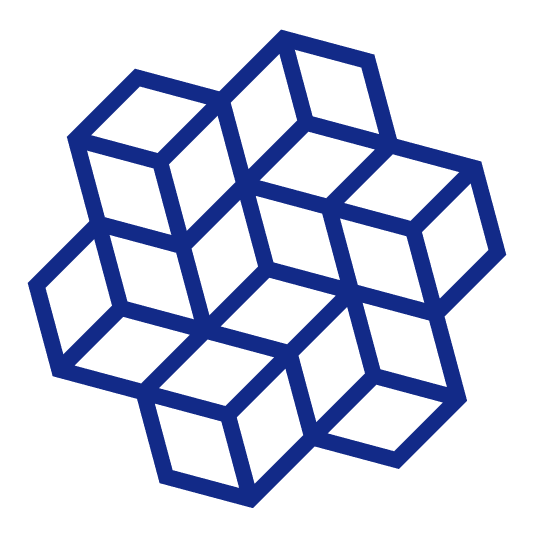






.jpg)



.jpg)